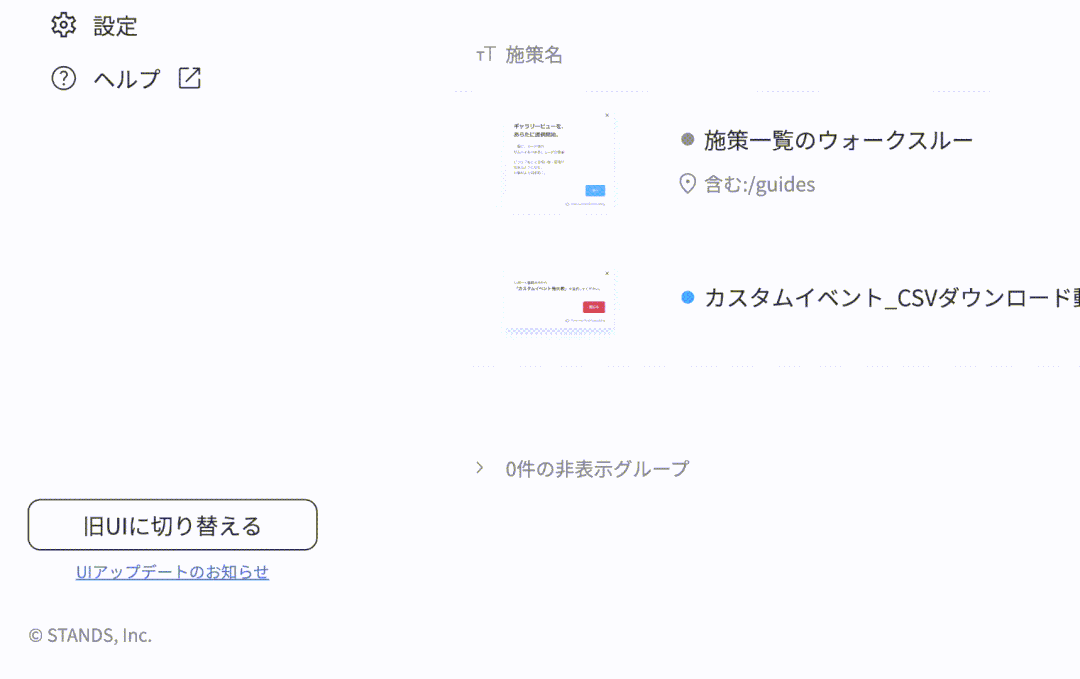先日、OnboardingというノーコードプロダクトのUIアップデートを行いました。
このアップデート、実は単純にUIを変更したわけではなく、既存ユーザーのUXに配慮した形でリリースされました。それが ”オプトアウト” という手法です。
UIのオプトアウト
概要
オプトアウトとは、提供されたものをユーザーが拒否することが出来る仕組み、あるいは拒否する行為を指します。
つまりUIアップデートのオプトアウトというのは、新しいUIを拒否し旧いUIを利用することができる仕組みを指します。
効果
新しいUIは、程度の差こそあれ必ず既存ユーザーの反発を生みます。
これは、何かを得たいと思う気持ちよりも、一度得たものを失いたくない気持ちが上回るという、ヒトの認知バイアスが原因です。このバイアスは”損失忌避性”と呼ばれます。
新しいUIによって、既存ユーザーは「慣れていたUIや覚えた操作を失う」こととなるため、このバイアスに引っかかって急激なストレスとなるわけです。
すべてのアップデートが強いストレスになるわけではありませんが、何かが無くなったり、変更の範囲・量が大きくなるほどストレスのレベルは高まります。
オプトアウトは、新しいUIを使うのか旧いUIを使うのか選択することが出来るため、このUIアップデート時のストレスを下げることが出来るのです。
実践
私たちにおいては、このオプトアウト導線をナビゲーションバー最下に配置して新しいUIを提供しました。
既存ユーザーはこの導線から、旧いUIへいつでも戻すことができます。
ナッジ
ちなみに、オプトアウトの対比となる手法に”オプトイン”があります。これはオプトアウトとは反対に、提供されることを受け容れることです。
今回の話で言えば「私は新UIを使います」と宣言した場合にのみ新UIが提供される という像ですね。
今回このオプトインにしなかったのは、行動経済学的にヒトは様々な心理からデフォルト状態を受け入れやすい という性質を鑑み、これを利用して新UIを使いたくなるようナッジ1を働かせたかったためです。
今回私たちは新しいUIの方がユーザーの生産性が高いことをリサーチ段階で把握していました。つまり新UIを使う方がユーザーにとって利益が大きいので、出来るだけこちらを使うよう導きたいわけですね。
しかし、強要すれば上記のような損失忌避性によるストレスが無条件にユーザーにかかってしまうため、オプトアウトの選択肢を示しつつ、新UIを使うというよりよい選択へとそれとなく誘導しているわけです。
ヒトが望ましい行動をとれるよう、ゆるやかに誘導・後押しするアプローチ。行動経済学的手法・概念の1つ。